安部 修仁(あべ しゅうじ、1949年9月14日- )は、日本の実業家。株式会社吉野家ホールディングス会長、社長を歴任した
福岡県出身。
福岡県立香椎工業高等学校卒業、日本大学経済学部中途退学。
高校卒業後、プロのミュージシャンを目指して上京、R&Bバンドを結成して活動する傍ら、吉野家でアルバイトとして働いていた。
その後、音楽の道を諦めた安部は、正社員として株式会社吉野家(吉野家ディーアンドシーを経て現在の吉野家ホールディングス)へ入社した。
1977年(昭和52年)からは九州地区本部長を務め、1980年(昭和55年)には同社倒産を経験した。
1983年(昭和58年)には取締役として経営参加。
その後セゾングループの出資により再建された同社で1988年(昭和63年)の常務取締役就任を経て、1991年(平成3年)には、当時42歳で代表取締役社長に生え抜きで就任。
以降、22年間にわたり吉野家の経営を指揮し、「ミスター牛丼」と称された。
2007年(平成19年)10月の持株会社化により、吉野家ホールディングス社長に就任(事業会社を分割したため事実上は続投)。
新会社の吉野家の社長には出射孝次郎が就任し、自身は吉野家事業から撤退していたが、2010年(平成22年)4月より株式会社吉野家の社長を兼任することとなり、再び吉野家事業に携わった。
2012年9月1日付で代表権のある会長に就任。
2014年5月にはHD会長を退き、取締役から外れ、同年8月31日付で事業会社「吉野家」の社長からも退くと発表した。
またこれと同時に、かつて倒産を経験した幹部たちも安部の退任に合わせて退くことが明らかとされている。
新卒採用を経ていない非正規アルバイトからの叩き上げで社長となった事で、注目されている人物である。
特に、東証1部上場企業において非正規雇用出身者が経営トップに就くのは非常にまれなケースである。
他に、東証1部上場企業において、非正規雇用から代表取締役等のトップに就任した例はブックオフコーポレーションの橋本真由美等がいる(※但し、両者とも入社時から上場の大企業であった訳ではない)。
- 仕事を楽しくするには
- ハードに仕事することの重要性
- 提案してみることの重要性
- 難しいことに挑戦して達成したときの方が喜びは大きい
- 仕事が面白くなると、幸福感がより大きくなる
- 仕事時間の密度を濃くした方が楽しいのでは
- 働き方自体を評価の対象にしてはいけない
- 向上心の強い人は、仕事を単なる労働とは考えていない
- どんな環境下でも自力で仕事を面白くすることは可能
- 経営者にごまかしがあると企業として本当の力が出ない
- バランスシートでごまかす会社は誰も本気にならない
- 外食や小売業に過重労働が蔓延しやすい理由
- 経営者がごまかしで搾取しようとしているのか、そうでないのかが非常に重要
- やりたい仕事があったら直訴することが大切
- 嫌なこと、苦手なことを後回ししないことの重要性
- 勝つまでやるから勝つ
- 数字は翻訳してから伝える
- 数字はコミュニケーションツール
- 買収先のブランドを絞る理由
- 企業を買収するときの必須条件
- 短期的に株価を上げようとは思っていない
- 株式時価総額を増やすことより、事業の経営が先
- キャッシュを潤沢に持つ必要性
- 厳しい経営基準を採用する
- お客さんとメンタルなつながりを大事にしたい
- 収益が許す限り伝統を大事にしたい
- 券売機を入れない理由
- 仮説は実際にテストをしてから実行する
- 吉野家の最優先事項
- 企業改革は自己否定からスタートする
- 作業を最小単位に分解して業務スピードをアップさせる
- 業務改善の第一ステップは細分化
仕事を楽しくするには
経験論でいいますが、自分の限界を小さく設定するほど、仕事はつまらなくなっていき、やらされ感が増大していきます。
反対に、会社から与えられた仕事の範囲をはみ出して、周囲の仕事にまで好奇心をもって積極的に提案活動を行っていくと、仕事はどんどん面白くなっていきます。
ハードに仕事することの重要性
ある時期、集中的にハードに働くとスキルが急激にアップします。
つまり、量が質に転化する瞬間があるわけで、これも忘れてはならないことだと思います。
提案してみることの重要性
最終判断を下すのは上位者ですから、提案なんていくらでもやってもかまいません。
採用されなければゼロ、採用されればプラスですから。
会社にとってマイナスになることは絶対にありません。
難しいことに挑戦して達成したときの方が喜びは大きい
私自身、確信犯的に自分の職務範囲をはみ出して、自分勝手に挑戦を続けてきました。
だって、簡単なことを達成したときよりも、難しいことに挑戦して、それを達成したときの方が喜びは大きいでしょう。
仕事が面白くなると、幸福感がより大きくなる
仕事が面白くなると、思考の幅も深さも大きくなり、人生で得られる幸福感がより大きくなると私は思っています。
仕事時間の密度を濃くした方が楽しいのでは
仕事は生活の糧を得る手段であると割り切って、プライベートの時間を大切にするのが俺の生き方だという考え方は誰も否定できません。
ただ、あくまでも私見ですが、ビジネスマンは人生の大半を会社の中で過ごすわけです。
その時間の密度を濃くしたほうが、楽しいのではないでしょうか。
働き方自体を評価の対象にしてはいけない
マネジメントは働き方自体を評価の対象にしてはいけません。
評価はあくまでも客観的、定量的、定性的に行われるべきです。
向上心の強い連中の働き方自体を評価してしまうと、暗黙のうちに過重労働を強いることになってしまいます。
向上心の強い人は、仕事を単なる労働とは考えていない
向上心の強い連中は、どんな組織にいても、仕事を単なる労働とは考えません。
そういう人間は、5年、10年経つと必ず会社の中で頭角を現してきます。
すると、必然的により大きな仕事を任されるようになります。
だから、一層仕事が面白くなっていきます。
どんな環境下でも自力で仕事を面白くすることは可能
大企業で働いていても、常に問題意識を持ち自分の仕事以外にも好奇心を向けることは可能だと思います。
たとえ仕事の範囲が厳格に定められていても、その範囲の中で独自に課題を設定し、それを解決していくことはできます。
つまり、どんな環境下でも、自力で仕事を面白くすることは可能です。
経営者にごまかしがあると企業として本当の力が出ない
実態的にかかった人件費はきちんとコストとして計上し、全額をきちんと支払う。
そこを厳密にやった方が、設定した目標に対して、全社員が前向きに取り組めるようになります。
経営者にごまかしがあると、企業として本当の力が出ないのです。
バランスシートでごまかす会社は誰も本気にならない
実態的に過重労働を強いているにもかかわらず、それをきちんとコストとして計上せずにバランスシートを作成し、収益が上がったように見せかけていると、収益もごまかしの数字になってしまいます。
これは仮に収益を5%アップしようと目標を立てても、そもそもごまかしが前提だから、誰も本気にはなりません。
外食や小売業に過重労働が蔓延しやすい理由
外食や小売業界の一部は、最も過重労働が蔓延しやすい体質を持っています。
経営者が低コスト化を実現するために、実態的には労働搾取を行っているのに、それをごまかしているケースが多い。
残業時間を語るときには、まず、その企業で公平な分配が行われているか否かを見定める必要があります。
経営者がごまかしで搾取しようとしているのか、そうでないのかが非常に重要
私が20代後半のころ、吉野家は急成長企業でしたから、社員も大きな希望を持っていました。
それに、吉野家を企業化した先代の松田瑞穂社長は、教育投資、報酬制度、利益の配分といった面で、社員の成長に必要な環境を非常によく整備してくださる方でした。
それらをトータルに考えると、決して労働搾取されていたとは思いません。
やはり、残業や過重労働の問題を考えるときは、経営者がごまかしで搾取しようとしているのか、そうでないのかが非常に重要だと思います。
やりたい仕事があったら直訴することが大切
私が28歳のころ、当時の吉野家は九州に一店舗も持っていなかったのですが、私の郷里は福岡なので、休暇で実家に帰ったとき、勝手に提案書を書いて九州の店舗計画を私にやらせてほしいと社長に直訴しました。
いま思えば稚拙な提案書でしたが、社長のOKが出て、九州地区本部長になりました。
嫌なこと、苦手なことを後回ししないことの重要性
労働時間の削減を最も阻害するものは、嫌なこと、苦手なことを後回しにすることです。
勝つまでやるから勝つ
数字は翻訳してから伝える
数字だけを伝えると、今度は手段の目的化という現象が起こってくる。
数字はあくまで手段であって目的ではありません。
だから、数字は必ず目的と一緒に伝えなくてはなりません。
数字を使うときには、きちっと翻訳してやることが大切なのです。
数字はコミュニケーションツール
数字は最も重要なコミュニケーションの道具です。
言葉だけを伝えると、まったく逆の解釈をされるといったことがしょっちゅう起こってしまいます。
ですから、個々の役割を明確にするためには、数字で目標を伝えることが不可欠です。
買収先のブランドを絞る理由
(買収した企業のブランドを極力絞り込むのは)その部門ごとのトップブランドになってほしいからです。
ただし、絶対売上と絶対利益を大きくしろという意味ではありません。
一店当たりの来客数と利益率が、相対的に最も高いという意味でのブランドを指すのです。
企業を買収するときの必須条件
我々と関わることで、相手のビジネスがさらに高まり、我々もよくなることが企業買収の必須条件です。
補完しあいながら有効にドッキングするということです。
短期的に株価を上げようとは思っていない
むろん時価総額は高いことに越したことはありませんが、短期的に株価を上げようとは思っていません。
我々は長期的に株価を上げるとこに判断の軸を置いた経営を標榜するということです。
もし、株主が短期的に株価を上げることを望むのであれば、僕らに経営をさせない方がいい。
株式時価総額を増やすことより、事業の経営が先
うちは事業の経営をやっているのであって、株式時価総額を増やすことがトップ・プライオリティ(最優先事項)ではありません。
株式時価総額主義とは、一線を画しています。
キャッシュを潤沢に持つ必要性
2から3年は商売しなくても、社員の給料は払えます。
手元流動性が高い形で資産を持っていると、いざというとき時間が稼げます。
牛丼販売停止のあと、デッドストックを出しつつも新メニューを軌道に乗せることを優先できたのは、キャッシュを潤沢に持っていたからです。
つまりそれをやらなきゃ死んじゃうというとき、赤字を出してでも生命の維持・継続に集中できる。
厳しい経営基準を採用する
会社更生法申請以降、出店基準をROI(投下資本利益率)20%以上、営業利益10%以上と定めたわけですが、この基準はいまでも変えていません。
言い換えれば、営業キャッシュフロー重視の経営を志向しているということです。
お客さんとメンタルなつながりを大事にしたい
牛丼を食べる刹那的な時間であるけれど、お客さんとのメンタルなつながりを大事にしていきたい。
そういうマインドを、心根のところで共有していきたい。
収益が許す限り伝統を大事にしたい
文化人の方々は、吉野家は無機質この上ないとおっしゃるわけですが、築地で生まれた吉野家には、伝統的にかもし出してきたひとつの文化があると思うんです。
券売機を置かないのは、その文化を収益が許す限り大事にしていきたいというメッセージでもあるんです。
券売機を入れない理由
券売機を置いた方が作業の煩雑性ははるかに小さくなるから、労働生産性を徹底的に追求している我々としては本来、券売機は必然の道具です。
しかし、非常に矛盾に満ちたことではありますが、券売機を置かないことで大事にしたいことがあるんです。
仮説は実際にテストをしてから実行する
仮説ってものほどあてにならないものはないから、仮説検証には相当ボリュームをかけます。
280円のときは4タイプの価格実験を30店舗でやりました。
粗利が一番大きくなる合理的なプライスポイントは一直線には出てこなくて、跛行性(はこうせい。つり合いのとれていない状態のまま進行すること)がある。
たとえば、270円と280円で客数は変わらないが、290円と300円の間には壁がある。
つまり、とびとびに出て来る。
その中から、あるレンジ(範囲)に収まる価格を選び出すのです。
吉野家の最優先事項
お客さんの期待を裏切らないのが、うちのトップ・プライオリティ(最優先事項)です。
企業改革は自己否定からスタートする
ドラスティック(徹底的)な革新運動はそれまでの常識を持ち出して、はなから無理だとしてしまったからできないんですね。
そこで、現状肯定と過去習慣の延長は全部ご破算にして、おおっぴらに自己否定をするところから始めました。
こうでなければ我々は成立できないという目標と枠組みを作って全員を追い込みました。
作業を最小単位に分解して業務スピードをアップさせる
作業工程の無駄を徹底的になくし、生産性を向上させるために、作業をすべて分解するところから始めました。
たとえば、フロアモップがけという作業については、道具の運搬、人の移動、洗浄作業などの作業に分解し、ワークスケジュールの流れと組み合わせて、作業時間の短縮に取り組みました。
業務改善の第一ステップは細分化
作業をブレークダウン(細分化)して最小単位の作業項目に置きなおし、作業項目を少なくする作業にも取り組みました。
こうして想定できるイメージの限界ギリギリのところに終着点があるのだと考えて、高い目標を掲げて改善運動を進めていったんです。


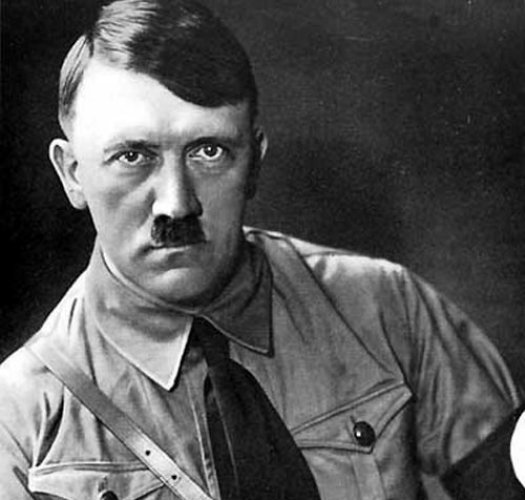

コメント